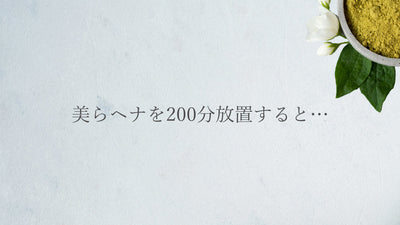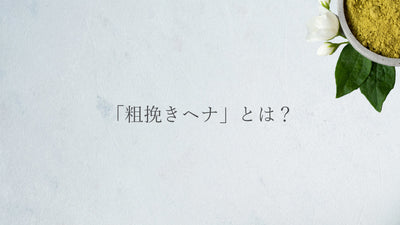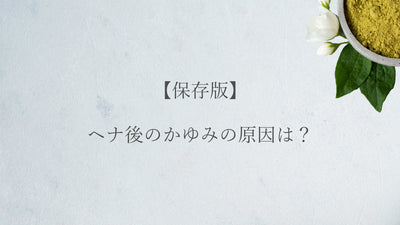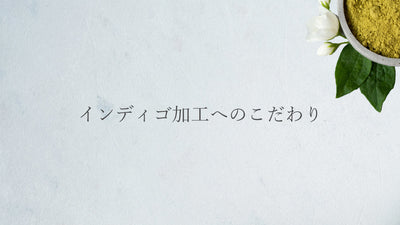「粗挽きヘナ」とは?
「『粗挽きヘナ』ってどうなんですか?」
ある日、このような質問を受けました。
粗挽きヘナは、沖縄近くの離島で作られています。
今回は、この粗挽きヘナについて解説していきます。
まず、分かりやすく珈琲で例えてみます。
「粗挽き珈琲」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

実は、珈琲豆の挽き方は5段階あります。
①極細挽き(ごくぼそびき)
②細挽き(ほそびき)
③中細挽き(ちゅうぼそびき)
④中挽き(ちゅうびき)
⑤粗挽き(あらびき)
コーヒー豆を挽くのは、
コーヒーの成分を抜き出しやすくするためです。
豆を挽かなくても抽出することはできますが、
時間がかかる上に、抽出が不十分になります。
豆を粉状に細かくすることで、お湯と接する表面積を増やし、
成分を抽出しやすくしているのです。
挽いたコーヒー豆の粒の大きさ(粒度)が、
小さく(細挽きに)なるほど、
コーヒー豆の表面積は増えます。
例えば、丸いボールを半分に切ると切断面ができますよね。
それをまた半分に切ると、さらに表面積が大きくなります。
このように、
粒が小さければ小さいほど、お湯との接触面も増え、
抽出効率が高くなり濃いめの味わいになります。
逆に、粒度が大きく(粗挽きに)なるほど、
抽出効率は下がり、
軽めのあっさりした味わいになります。
珈琲の細挽きは、時間をかけてゆっくりお湯を入れると、
苦味・渋味・えぐ味などが出てしまいます。
一方、粗挽きにするとお湯が浸透しにくく
抽出に時間がかかるため、軽くすっきりとした味わいになります。
つまり、珈琲の粗挽きは
意図的に抽出を制限するするための粉砕方法なのです。
ヘナの粗挽きと微粉砕の違いも、これと同じです。
ヘナの葉をお湯に浸けておけば、染料はゆっくり抽出されますが、
数時間置いても薄い抽出になります。
これは珈琲の粗挽きに近いです。
一方、乾燥してパウダー状にすると染料の抽出は早くなります。
こちらは珈琲の細挽きに近いです。
このように、粒度の大きな粗挽きでは、
染料の抽出に時間がかかります。
インド産の、80〜100メッシュ(150ミクロン程度)のヘナでは、
お湯を加えて45時間ほど熟成すると最も濃く染まります。
※メッシュとは、ふるいの目の細かさを指します。
メッシュの数字が大きいほど目が細かく、粒子が小さいです。
また、ミクロンとは大きさの単位(1/1000mm)です。
天日乾燥の場合は、葉にある程度の水分が残っています。
これを粉砕機にかけると、粒の大きさ(粒度)は平均170ミクロンになります。
これは、80メッシュのふるいが通る大きさです。
100メッシュのふるいにかけると、大きな粒が通過できずに残ります。
インド産のヘナのほとんどが、このタイプです。
私のヘナパウダーコレクションの中で
最も粒が粗いのが石臼挽きのヘナで、
次に当該の粗挽きヘナです。
(他の国産、外国産ヘナは
80(170ミクロン)~100メッシュ(150ミクロン)です。)
ちなみに、沖縄産美らヘナは
300メッシュ(45ミクロン)です。
かなりきめ細かいことが分かっていただけるでしょうか。
この場合、6時間ほどで最も濃く染まります。
これは、パウダーの粒が細かく表面積が大きくなり、
内容成分の抽出時間が大幅に短縮されるからです。
ここで、ヘナの大きさ(粒度)を確かめる方法をご紹介します。
ヘナ粉100gに温湯を加える量で、粒度の細かさが分かります。
・加える温湯が400ml以上→粗挽きヘナ
・加える温湯が350ml→一般的なヘナ(80メッシュ)
・加える温湯が300ml→一般的なヘナ(100メッシュ)
・加える温湯が230ml→沖縄産美らヘナ(300メッシュ)
粗挽きになればなるほど、加える温湯が多くなります。
温湯が多い分、染料が薄くなり、白髪も薄く染まるのです。
ちなみに…
インド産ヘナは、温湯を加えて撹拌した直後は粘りがあります。
しかし、その粘りは時間の経過とともになくなってきます。

私の実験では、インド産(80~100メッシュ)のヘナパウダーであれば、
温湯を加えて攪拌した直後よりも、45時間ほど熟成させた方が
30%濃く染まります。
粘りがあるときは、染料がまだ抽出できていない状態です。
このときに、すぐに毛髪へ塗布するのは得策ではありません。
ヘナを粗挽きにすると染料の抽出に時間がかかるので、
ヘナペーストを作って熟成させた後、お使いになることをオススメします。
【ヘナパウダーはお湯に溶けてはいない】
驚かれるかもしれませんが、
ヘナ粉はお湯に溶けることはありません。
超微粉のヘナ粉であっても、粗挽きであっても、
ヘナパウダーに温湯を加えても、
長時間熟成しても、それは変わりません。

こちらの写真は、美らヘナとインド産ヘナの比較です。
左が美らヘナ(300メッシュ、45ミクロン)
右がインド産ヘナ(100メッシュ、150ミクロン)です。

拡大してよくご覧下さい。
ヘナ粉が溶けていないのがお分かりになるかと思います。
さらに拡大します。
こちらはインド産ヘナ(150ミクロン)です。
つぶつぶが肉眼で確認できます。

↓45ミクロンの美らヘナであっても、細かいつぶつぶが見えます。

粗いヘナ粉も細かいヘナ粉も、お湯に溶けることはありません。
では、この2つの違いは何でしょうか?
それは、お湯を加えて攪拌してからの成分抽出の時間です。
ヘナの染料は、粒が粗いと抽出に時間が掛かり、
細かいと時間短縮されるのです。
粗挽き、石挽きヘナの場合は、これらのヘナに比べて、
もっと粒が大きく、抽出により長い時間を要します。
さて、ここでヘナパウダーが細かくなることの、
大きなメリットについてお話します。
それは、
「へナパウダーを細かくすれば、トリートメント効果が高まる」
ということです。
私は、ヘナパウダーを細かくするために
様々な努力を行っています。
実は、どんなに優れた粉砕機を用いても、
ヘナ葉に含まれる水分量が多い場合は
微粉砕することは出来ません。
つまり、天日乾燥では150メッシュ(100ミクロン)より
細かいパウダーを製造することは物理的に不可能なのです。
今回、美らヘナの300メッシュ(45ミクロン)を実現できたのは、
粉砕機メーカーさんやふるいメーカーさんからのアドバイス、
その他、南風原のヘナの師匠、
それから多くの理美容師さんのお陰です。

また、当然ですが、パウダーを細かくするほど、
製造コストは高くなります。
なぜなら、ヘナの葉を段階的に乾燥させるため、
「一次乾燥」と「二次乾燥」という2つの工程が必要だからです。
これらの工程には、それぞれ乾燥施設が必要となり、
設備投資や光熱費も大きくかかります。
さらに、微粉を製造するための装置も必要です。
実は、2025年5月から、ヘナ製造のため、
新しい冷却式超微粒子粉砕機を導入しています。
よりよいヘナの実現のため、今後も更なる品質向上に励みます。

美らヘナ、うるまヘナは少しずつ、確実に一歩一歩前進しています。
みなさんどうぞ今後ともよろしく応援お願いします。
本日も今日もご覧頂きましてありがとうございました。